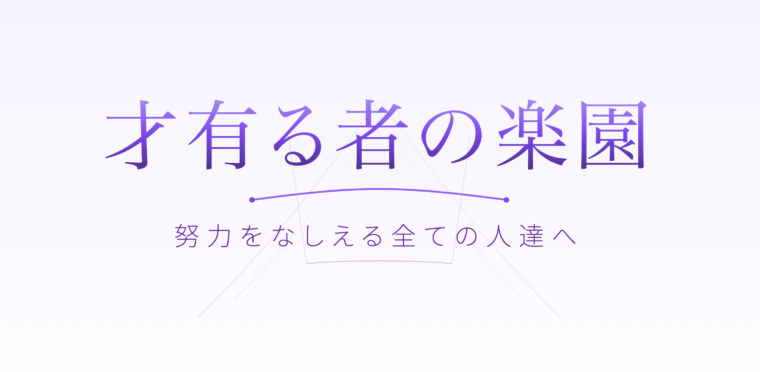昔、書いていたブログより抜粋。 米や食に関する事業は今年から再開したい。
——–
2020.06.15
在來種とは何ぞや?
よく無農薬栽培の作物や加工品を作っておられる方が、幻の◎◎、昔ながらの〜〜、在來種◎◎なんていう触れ込みを見かける。
F1は駄目で、在來種固定種が大切で〜、という話もそういった界隈ではよく聞く。
ただ、在來種という言葉を使っている人に、在來種とは何ですか?という質問をした際に、明確に答えてくれる人に今まで出会ったことが無い。
何となく古い、なんとなく昔から作っているかもみたいな。
勿論、そういった人達は、巷の人々に比べれば、よほど良いことをしていると思うのだけれど、自分が使う言葉ぐらいはしっかりと考えて欲しい。
日本における在來種とは何か?
これには明確な答えがある。
”江戸時代以前から自生、或いは栽培されている作物である。”
在來の種なので、極論30年前からその地域にあったものを在來種と語ることは別に違法では無い。
なかには、コシヒカリ、やたらと新しい米を幻の在來種と呼称してブランド化している人もいる。
ただ月日は流れるし、皆が別々の事を言えば、求める人は混乱する。
なので、私は、日本の在來種とは、”江戸時代以前から自生、或いは栽培されている作物である。”と明言していることにしている。
では、明治以降の作物が全て悪いか?
勿論、そんなことは無い。ただ、明確な線引きをしておかないと、後世の人が困るのです。
線引きは、時代(出来事)で区切るか、年数で区切るかしないといけない。ただ、年数の場合は、相対的なので、絶対的な時間が軸がある方が良い。
在來種という言葉が一番使われるのは稻(米)である。
なので、品種で云うと、
關取(雲龍)は、命名年が1848年なので、在來種。
雄町(山田錦の父親)は、命名年が1859年なので、在來種。
名倉穗、巾着、赤ひばりなども、江戸時代以前の在來種である。
よく在來種と間違えられるのは、
龜の尾と旭(朝日)の2品種。西の旭、東の亀の尾とも言われていた。
亀の尾は、阿部亀治さんが明治26年(1893年)に在來種惣兵衛早生から選抜&命名なので、厳密には在來種では無い。
旭(旭)も山本新次郎さんが明治42年(1909年)に在來種日の出から選抜&命名なので、これも在來種では無い。
この2つは共に、(在來種の)明治選抜種と呼称するのが正しい。
餘談だが、龜の尾は明治三大品種と云われ、
龜の尾(かめのお)、神力(しんりき)、愛國(あいこく)と並んで大層美味であると云われている。私は、龜の尾と神力を食したことがあるが、明治らしい洗練された味が好きである。
というより、明治以前のお米は各地域とっておきのお米があり、今の時代の甘くてネバネバした不味い米とは一線を画す奥深い旨みがある。
例えば、伊勢(三重)の三穗と云われるのが、
伊勢錦(イセヒカリでは無い)
關取(雲龍)
竹成である。
竹成だけ明治選抜種であるが、これも大層美味だと予想されるが、恐らく生産者は日本で数人でしょう。
因みに、明治の品種は洗練されていたエリート米といった感じで、端的に美味い。
江戸以前の米は、美味い上にとっても遊び心を感じる。
昭和以降の育成種でも美味しい米は勿論ありますよ。
米について話すと長くなるので、詳しくは、また次回以降に書きますね。
けっきょく在來種って何?
と云われたら、定義は書いた通りだけど、江戸時代以前の人達からの贈り物。
そう考えるのが一番浪漫があって素敵だと思う。
お後が宜しいようで。
寫眞は、在來種關取と真鯛の刺身。それを丼にしてみた。2016年頃の寫眞です。
(※写真は、追って添付予定。2025/04/21 山本)
兀突骨